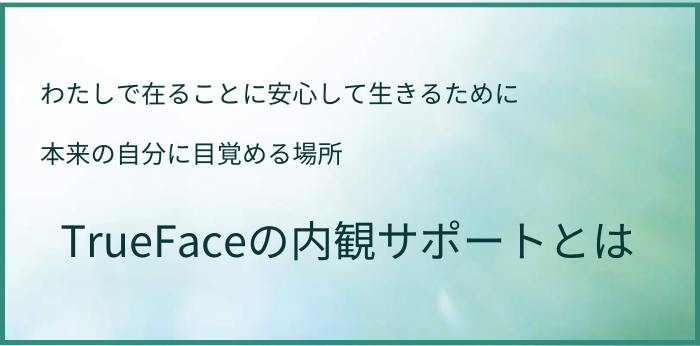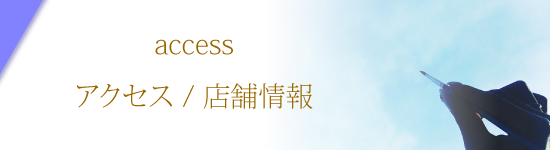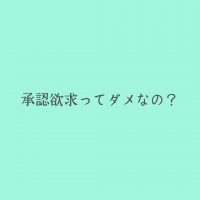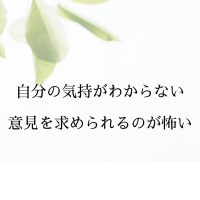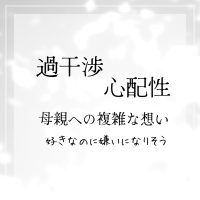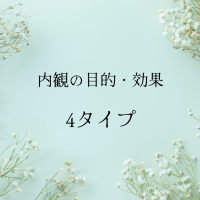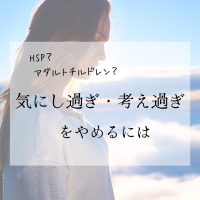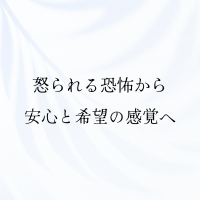内観(自分の心と向き合う)時にはいくつかのポイントがあります。この記事では、内観をする時に押さえておきたいチェックポイントを大まかにご紹介します。
内観ポイント①心の動きに着目する
内観は自分の心がどんな動きをしているかに着目します。例えば、仕事の悩みがあって内観する場合は、悩ましい状況をどう好転させようか思考を働かせるのではなく、悩ましい状況に対して自分がどんな感情を抱いているか、どんな解釈や判断・発想を持っているかなどに焦点をあてて心の中の状態を把握しましょう。
内観ポイント② 心を動かした対象を見極める
何に対して心が動いたのかを見聞分けることも内観の大切なポイントです。例えば、女子会の帰り道に何となく心が重くなってひとり反省会してしまう・・・。なんて場合は、その場の会話のながれに反応したのか、誰かの言葉に反応したのか、または自分の心の中の「もしも〇〇だったらどうしよう」という想像癖が発生しているのかなど、
心が重くなったきっかけを把握しましょう。
内観ポイント③ 掘り下げる
表面的な感情や思考を整理するだけでも、頭のグルグルが静かになるのでラクにはなりますが、表面対処に過ぎません。自分の主観を作り上げた背後には様々な要因があります。
思っていることや感じていることは、なぜそう思って、なぜそう感じたのか。普段は気に留めることもなく「だって普通はこう思うのが当然でしょ!」といってしまいたくなるような自分の当たり前に、敢えて自ら問いを立てていく。これが掘り下げです。
掘り下げは少しコツが必要なのですが、決まった形式にはめ込むと自分の「らしさ」をくみ取りにくいので、出来れば質問力を向上させる方が本質的な内観が出来るようになります。
TrueFaceが伝えたい内観の醍醐味とは
内観はパワフルなメンタルケアのツールになるし、ちょっと気持ちの整理をしたからってどうにもならなかったような心の違和感をもクリアに出来る素晴らしい取り組みです。しかし、本当の醍醐味実は自分の喜びも悩ましさも心も体も、自分が織りなす全てが自分という生き物の独自性や独創性を語ってくれていたことに気づくことだと思っています。
ぜひ人生メンタルケアを取り入れて、本来の自分に目覚める気づきを深めましょう。そして、あなたらしさを思いっきり楽しんで下さい。
承認欲求が強い自分が嫌い。人目なんか気にせずに気楽になるにはどうすればいいの?